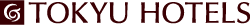腹巻買いますか?それとも……
- 腹巻屋。
団扇屋。
太刀屋。
鯛屋。
烏帽子屋。
鉢屋。
墨絵屋。
瓦屋。 - ここに挙げたのは、鎌倉時代の中頃、奈良の東大寺転害門*1付近で商売をしていた家で、すべて同じ業種です。さて、その業種とはなんでしょう?
- 「うーん、腹巻屋は腹巻鎧(腹部を守る武具)を、太刀屋といえば刀を売る店だろうから、すべて同じ業種というのは……、あっ、分かった! それらの品を扱う『問屋』ということですね」
- はい、ご名答。でも半分正解です。確かにこれらは問屋ではありますが、実はいずれも、旅人を泊める「宿屋」でもありました。
- 時は、長く続いた荘園支配に武士が割り入ってきた時代。
- 小田原の北条、甲斐の武田、駿河の今川、越後の上杉、美濃の斎藤といった強大な勢力の館があるところを中心に経済圏が成立して、動く物資の量も多くなり、これらを取り扱うために「問丸*2」(現代でいう問屋)が発達しました。
- そうすると当然、商人、特に行商人が爆発的に増えるわけですが、それに伴い増えた宿泊需要を問屋が引き受けたのです。
*1 転害門【てがいもん】
- 三間一戸八脚門の形式をもつ堂々とした門で、天平時代の東大寺の伽藍建築を想像できる唯一の遺構。平城京の佐保路(さほじ)に面したことから佐保路門ともいい、源頼朝を刺し殺そうとして平景清(たいらのかげきよ)が潜んだとの伝説から景清門ともいわれている。
*2 問丸【といまる 】
- 平安時代後期から発達した商業組織。年貢米の陸揚地である河川・港の近くの都市を拠点に運送、倉庫、委託販売業を兼ねた。後の「問屋」(とんや)の原型である。
フロイスも泊まった街道筋の商人宿

- さて、奈良には昔から小商売が多かったようで、後に松尾芭蕉*3らがこう詠んでいます。
- 奈良がよひ
おなじつらなる
細基手
ことしは雨の
ふらぬ六月 - 「細基手」とは、わずかばかりの資本で行う小商売。懐具合の寂しい行商人が連々と、土埃立つ初夏の奈良の街道を歩くさまが目に浮かぶようです。
- 奈良と同様に京都や堺、小田原、山口、博多といった商業で潤う町では、宿屋を兼ねる問屋が発展していきました。その一方で、主要な街道筋の宿屋が新たに問屋に参入するという逆形態も多くなっていったようです。
- そんな商人宿に、宣教師として来日し、日本の様子を世界に紹介したルイス・フロイス*4も宿泊したことがあったようです。塩屋だったか、風呂屋だったか、とにかく商人であふれかえる宿で、
「人の出入りの騒がしいことはバビロン*5の混雑に等しい」
と、フロイスはイエズス会への書簡で述べています。 
- チェックイン・チェックアウトの時間はまちまちで、その際には荷物の上げ下ろしでドタバタ。ようやく落ち着いたかと思うと商取引が賑やかに始まり、一方では集まって博打を始める者も……。
- 普通の旅人にはたまったものではなかったかもしれません。しかし商人には勝手知ったる気安い宿で、情報交換や息抜きに欠かせない場でもあったことでしょう。
*3 松尾芭蕉【まつお・ばしょう】(1644~1694)
- 江戸時代前期の俳諧師。伊賀国阿拝郡(現在の三重県伊賀市)出身。「蕉風」と呼ばれる芸術性の極めて高い句風を確立した、世界的にも知られる俳聖。晩年に河合曾良を伴い東北から北陸を経て美濃国までを巡った旅を記した紀行文『おくのほそ道』が特に有名である。
*4 ルイス・フロイス【Luís Fróis】(1532~1597)
- ポルトガルのカトリック司祭、宣教師。イエズス会士として戦国時代の日本で布教し、織田信長や豊臣秀吉らと会見。戦国時代研究の貴重な資料となる『日本史』を記したことで有名。
*5 バビロン【Babylon】
- メソポタミア地方の古代都市。市域はバグダードの南方、ユーフラテス川をまたがり、紀元前17世紀から紀元7世紀頃まで栄えた。ルイス・フロイスは『日本史』の中でも、岐阜の町自体も「バビロンの雑踏のよう」と表現しており、混沌としていたであろう古代の大都市になぞらえた。

- 鎌倉時代から戦国の世にかけてのビジネスホテルは、まさにビジネスの場でもありました。それ故、なかなか現代のような一般の旅行客も落ち着いてくつろげる場ではなかったようですね。
- 次回は、中世最大の旅行イベント「お伊勢参り」に向かう旅人の宿にクローズアップ。内宮の宇治、外宮の山田。双方の御師が牛耳る伊勢神宮界隈の宿泊事情とは……。
参考文献/宮本常一著『日本の宿』(八坂書房)
- 宮本常一(みやもと・つねいち)
1907年、山口県周防大島生まれ。日本の民俗学者。日本観光文化研究所所長、武蔵野美術大学教授、日本常民文化研究所所長などを務める。1981年没。同年勲三等瑞宝章授与。
日本の宿、その歴史をひもとく
- illustrations=Noriyuki GOTO