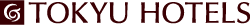「広さ=豊かさ」ではないと茶室が気づかせてくれた
- 熊本県のゆるキャラである「くまモン」のプロデュースや、映画『おくりびと』の脚本などで知られる小山薫堂氏。実は無類のホテル好きでもあり、ドラマや映画など、さまざまな角度から「ホテル」をテーマにしてきた。小山氏にとって理想のホテルとは、くつろぎの空間とはどんなものなのだろう?そんな問いを胸に事務所を訪ねてまず驚いたのは、マンションの部屋の真ん中に漆喰の壁に囲まれた茶室が構えられていたことだ。
- 「僕は8年前に京都の老舗料亭(下鴨茶寮)の経営を引き継ぎ、主人を務めています。茶道の世界に接しているうちに和の世界に強く惹かれました。洋風の世界観で育った僕たちは“広さは豊かさ”だと思い込んでいたけれど、茶室を見てそれは違うんだなと改めて感じました。茶室って四畳半でも広いぐらいで、二畳、三畳でも豊かな世界観を持っています。このオフィスは洋風の空間ですが、その中に茶室があると豊かさが加わるのではと思ってしつらえました。茶室の魅力は、ホテルの魅力にも通じるものがあると思います。その大きな理由は、どちらも日常のギアチェンジの場所だということ。僕は子どもの頃からホテルが好きで、東京のホテルに泊まりたいから東京の大学を受験したほど。ホテルは非日常の場所であり、そこに行くだけで気分や視点が変わったりする。事務所に茶室を作ることで、リフレッシュできる空間になったと思います」
ホテルが地域そのものの価値になる時代へ
- 振り返れば小山氏の仕事は、美食文化を広めた『料理の鉄人』や『パレ・ド・Z~おいしさの未来~』、理想のホテルを追い求める主人公を描いたテレビドラマ『東京ワンダーホテル』など、ホテル文化から派生したものが数多くある。その意味ではホテルは「種を蒔く場所」でもある。まさに少年時代からの「好奇心の原点」と言ってもいいだろう。
- 「ホテルというのはもともと西洋の文化ですが、実はサービスの原点である“他者を慮(おもんぱか)る力”は日本人の方が西洋人よりもあると思います。国土が狭く、木と紙の家に住んでいる国民ですから、生活の中で、他者の気配を感じ取る感覚を持っています。対して広い国で石とレンガの家に住んでいる人は個が強くなる。だからサービスの能力は、日本人は本来高いのではないでしょうか」
- そう語る小山氏は今、理想のホテルの姿をどう考えているのだろうか。「ほかの場所から訪れる人だけではなく、その地域に住んでいる街の人が感情移入できるホテルですね。ホテルを利用する人と街の人が分断されるのではなく、何らかの関係性を持てること。それが実は、お客様の満足にもつながると思うんです。
- 先日、若い人たちが古民家を譲り受けてホテルとして再生させた場所を訪れました。こういう古民家再生の取り組みは、ほかにもたくさんあると思いますが、そこが良かったのが、すごくおいしいパンの店を併設させていたこと。泊まっている人だけでなく、街の人もおいしいから買いにくる。すると宿泊客は“こんなにおいしいパンが買えて街の人は羨ましい”と思ったりする。よく地方の人は“こんな土地何もないから”って謙遜しますけど、宿泊客の素直な“羨ましい”という気持ちが街の人に伝わると、そのホテルは街の価値へと変わっていきます。それがきっかけになって移住する人が増えるとか、2地域居住(この街に別荘を持つ)というようなライフスタイルが生まれてくる。ニューヨークにある伝説のチェルシーホテルみたいに、その街の息吹が感じられる、人肌が感じられるホテルというのかな。その街の暮らしを疑似体験できるようなホテルが、これからの時代に必要のような気がします」
今こそ伝えたい「のさり」の精神
- 人や街の息吹が感じられる距離。しかしコロナ禍においては、物理的な距離を縮めることは難しい。そんな中で小山氏は、この時代に何を考え、日々を過ごしているのだろうか。「コロナは僕にとってはフィルターの役割を果たしました。本当に必要なものと必要ではないものをふるいにかけるフィルター。それによって自分自身の生活や行動についてひとつひとつ“これって本当に必要なの?”と問い直す機会になりました。
- そのふるいの目に残ったもののひとつに“手紙”があります。最近、あの伝説的イラストレーターでグラフィックデザイナーの黒田征太郎さんと文通をしているんです。きっかけは僕のラジオ番組にゲスト出演していただいたことで、“手紙書いてくださいよ、僕も書きますから”と言ったら本当に書いてくれて、週に2通か3通、必ず届きます。オリジナルの絵と短い文章が毎回違う紙に書いてあって、額装したらそのままアートです。焼酎を送ったら、飲んだ後の空き瓶のラベルに絵を描いて送り返してくれたことも。
- コロナで人と人のコミュニケーションが問い直されているけれど、手紙は“間”がすごくいい。書いてポストに投函してから想像するんです。今頃、自分の言葉はどの辺を旅しているのかな? なんて。メールだと返信がこないとムッとしたりするけれど、手紙は返事が来なくてもちっとも苦にならない。こういうリズムもまた、必要なものとして自分の身に返ってきたのかもしれません。
- そしてもうひとつ、コロナ禍だからこそ広めたいものがあります。それは僕の故郷、天草の方言“のさり”という言葉。“人生いいことも悪いこともあるけれど、すべては天からの授かりもの。しっかりと受け止めて生きていきましょう”という意味です。まさにコロナは“のさり”。キリスト教の弾圧や、島原の乱、時代の荒波を経験してきた天草だからこそ生まれた言葉のように思えます」
食を通して未来を語り合う場所を

明るい未来を想像して語り合えるそんな場を作り上げていきたい - コロナ禍においても多忙な小山氏だが、2025年に開催予定の「大阪・関西万博」のプロデューサーにも名を連ねている。テーマとして掲げている「いのちをつむぐ」には、どんな想いが込められているのだろう。「僕が担当するのは、食を通して命を考えられるような場所です。食はすごくキャッチーなコンテンツでありながら、飢餓の問題をはじめ、社会課題に密接につながっています。“食べるって何だろう” “おいしいって何だろう”という、根本的な問いかけを通して、あたりまえをリセットできるような経験を提供したい。あたりまえから一歩抜け出すことは、社会課題に対して、自分にももしかしたら何かができるかもしれないという気づきにつながります。とはいえ僕の企画の根幹は“いかに人を楽しませるか”なので、あまり堅苦しくなく、未来を想像して明るい気持ちになる展示にできたらいいなと日々考えているところです。万博を開く意味が何かと聞かれたら、“未来を語り合う機会を作ることができる”と答えられるのかなと思います。今の時代は、どうしても目先のことを考えるのに日々忙しく、未来、特に明るい未来を想像する機会が減っているように感じます。50年、100年先の未来がどうなっているのかを語り合い、考えて、想像して、ワクワクする。そういう機会を作っていきたいですね」

スタッフのひとりである「くんトン」。発想力と想像力が豊かで、日本の食や文化のマニアだそう。
KUNDO KOYAMA
- 1964年熊本県生まれ。放送作家として『料理の鉄人』『東京ワンダーホテル』など数多くの人気番組を企画・構成。脚本を手掛けた映画『おくりびと』で2009年にアカデミー賞外国語映画賞を受賞。5月29日より全国順次公開の映画『のさりの島』をプロデュース。京都芸術大学副学長を務めるほか、文化庁「日本遺産審査委員会」委員、2025年大阪・関西万博エリアフォーカスプロデューサーなどとしても活躍中。